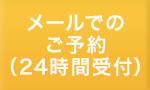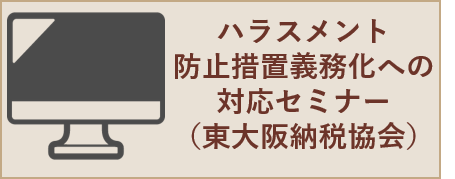懲戒解雇処分と退職金
Q X社は電鉄会社であり、社員のAは駅員として勤務している。Aが勤務時間外の電車乗車中に痴漢行為を行ったとして刑事罰に処せられたことが明らかとなった。X社はAを懲戒解雇としたうえで、X社就業規則に定める退職金の不支給・減額条項に基づきAの退職金を不支給としたい。いかなる法律的な問題があるか。
A 1 退職金は労働契約の終了に伴い会社が社員に支払う一定の金銭をいいます。その性格は一般的に、①賃金の後払い的性格、②功労報償的性格、③退職後の生活保障的性格があるとされています(小田急電鉄事件・東京高判平15.12.11・労判867-5)。退職金制度を設けるかどうかは会社の任意です。
制度を定めた場合でも支給基準、支給の有無が会社の裁量に委ねれられている場合には恩給的な給付として、労働基準法の規制を受ける「賃金」とはなりません(EX労基法第3章)。就業規則や労働協約で退職金の支給や支給基準が定められた場合には支払義務のある「賃金」となります。
2 退職金の不支給・減額については、まず退職金が「賃金」となる場合に賃金全額払い原則(労基法24条1項)に反しないかが問題となります。この点については、そもそも不支給・減額となれば退職金についての権利が発生していないと考えられるため、すでに発生している賃金を全額払うべきとする賃金全額払い原則の違反とはならないとされています。
また、退職金が賃金としての性格のほか、功労報償的な性格を有することから、退職金を不支給・減額とする条項を設けること自体が公序良俗に反するとまでいえないとされています(三晃社事件・最判昭52.8.9・裁判集民121-225)。
実際に退職金の不支給・減額条項を適用して、不支給・減額とする場合にも注意すべきことがあります。退職金が賃金の後払い的性格を有し、労働者の生活にも関するものであることから、適用が許されるのは、社員の永年の勤続の功を抹消・減殺してしまうほどの重大な不信行為があることを必要とします。
そこでは、社員の不信行為の態様や性質から会社への悪影響の程度を検討し、これまでの当該社員の勤務態度や実績から評価する勤続の功を抹消・減殺するものかを検討していきます。本事案の電鉄会社の例では、会社の勤務時間外に行った私生活上の行為が問題となっています。
私生活上の行為は一般に会社への不信行為とはいえませんが、駅員である者が電車で痴漢行為を行うという態様は電鉄会社であるXの業務に悪影響を与えるおそれがあります。他の諸事情も勘案して、実際にX社の業務への悪影響があったのかを検討していくことになります(参考:小田急電鉄事件・東京高判平15.12.11・労判867-5)。
裁判例の傾向としては、懲戒解雇が認められる場合には退職金の減額も認めるものが多く、不支給まで認める例は多くありません。全額の不支給を認めるのは会社に重大な問題が生じた場合であり、例としては、会社の仕入れに関し自己が代表者を務める会社に介在させ利益を上げていた事案(東京メディカルサービス・大幸商事事件・東京地判平3.4.8・労判590-45)、会社金銭を横領し、証拠隠滅の為に偽造伝票を作成した事案(千代田事件・東京地判平19.5.30・労判950-90)、社員が一斉退社し、別会社にデータを移した後に抹消した事案(日音事件・東京地判平18.1.25・労判912-63)などです。
3 事前の規定の整備関して、退職金の不支給・減額の規定は「退職手当の決定及び計算尾方法」として就業規則の相対的記載事項(その制度を設ける場合には記載しなければならない事項)となり、就業規則に記載する必要があります。そして、就業規則に支給の規定を設けた場合には、不支給・減額条項がない場合は不支給・減額することはできません。
4 本件では、どうしていけばよいでしょうか。まずはX社における退職金の性質を確認しましょう。賃金としての性格のほか、功労報償的な性格を有するといえるならば、退職金を不支給・減額とする条項を設けること自体が公序良俗に反するとまでいえないので、不支給・減額とすることは可能となります。
実際にAに対する不支給・減額が可能かは、社員の永年の勤続の功を抹消・減殺してしまうほどの重大な不信行為があるかで判断されます。具体的には、社員の不信行為の態様や性質から会社への悪影響の程度を検討し、これまでの当該社員の勤務態度や実績から評価する勤続の功を抹消・減殺するものかを検討していきます。
本事案の電鉄会社の例では、会社の勤務時間外に行った私生活上の行為が問題となっています。私生活上の行為は一般に会社への不信行為とはいえませんが、駅員である者が電車で痴漢行為を行うという態様は電鉄会社であるXの業務に悪影響を与えるおそれがあります。他の諸事情も勘案して、実際にX社の業務への悪影響があったのかを検討していくことになります(参考:小田急電鉄事件・東京高判平15.12.11・労判867-5)。
- 経歴詐称していた社員への対応
- 採用内定取り消し
- 試用期間の性質と運用
- 試用期間中の者の本採用拒否
- 上司の指示に従わない社員への対応
- 残業しない社員への対応
- 欠勤を繰り返す社員への対応
- 取引先から金品を受け取っている社員への対応
- セクハラ行為をする社員への対応
- 厳しい叱責をする社員への対応
- ストーカー行為をする社員への対応
- 会社行事に参加しない社員への対応
- 備品を私的利用する社員への対応
- 会社のパソコンやスマートフォンを私的に利用する社員への対応
- 配転拒否する社員への対応
- 出向を拒む社員への対応
- 休憩時間中の電話当番の賃金を要求する社員への対応
- 無断残業で残業代稼ぎする社員への対応
- 繁忙期に長期休暇を取得する社員への対応
- 復職を一方的に要求する社員への対応
- 時間外手当を要求する年俸制社員への対応
- 正社員同等の賃金を要求するパートタイム社員への対応
- 不正請求を行った社員の損害賠償義務の精算
- 通勤手当を不正受給した社員への対応
- 問題社員の解雇
- 普通解雇と懲戒解雇の選択
- 懲戒解雇処分と退職金
- 勤務成績の悪い者への退職勧奨
- 退職後の機密保持の義務付け
- 他の社員の引き抜きをする元社員への対応
- 休日に職場の同僚に物品等を販売する社員への対応
- 勤務時間外に兼業している社員への対応
- インターネットに開発中の商品に関する書き込みをする社員への対応
- インターネット上で会社や同僚を誹謗中傷する社員への対応
- 社内不倫する社員への対応