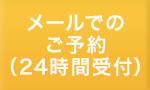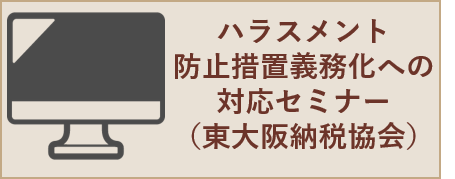試用期間の性質と運用
Q X社は次年度から大学新卒者の新規採用を始めたいと考えている。しかし、職歴のない学生の資質の見極めについて不安が残るため試用期間を設けたい。どのような点に注意すべきか。
A 1 試用期間の目的は一般に、労働者の能力・適性を見極めて、①本採用するかどうかを決定すること、②配属先を決定することです。法的性質としては、会社ごとの就業規則の文言や運用により細かい点で違いは生じるものの、解約権留保付の労働契約であると解されています(三菱樹脂事件・最判昭48.12.12・労判189-16)。つまり、本採用前とはいえ労働契約は成立しており、会社は社員との関係で解約権を有していることが特徴です。
この解約権の行使は無制限ではなく、労働契約を一方的に終了させることにあたることから解雇権濫用法理が適用されます。具体的には、上記試用期間の目的を前提に、解約権の行使が客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当と認められなければ、解約権の行使が濫用であるとして無効となります(労契法16条参照)。
2 試用期間の設定で、まず問題となるのは期間の長さと延長の問題です。試用期間中の労働者の地位は一般の正社員より不安定となるため、長すぎる試用期間の設定は無効となり、延長も制限されます。
長さに関しては、明確な基準はなく、ケースごとに試用期間の目的に照らして合理的な期間設定かどうかを検討することになります。裁判例では、6カ月から1年3か月の見習社員期間終了後にさらに6か月から1年の試用期間を定める設定が合理的範囲を超えていると判断したものがあります(ブラザー工業事件・名古屋地判昭59.3.23・労判439-64)。
試用期間の延長については、労働者にとってより不安定な期間が継続するので、有効性の判断は厳格になされます。裁判例では、1年の試用期間終了時には本採用しないと判断できるが、その後の勤務状況によっては本採用しても良いとして延長する場合、選考のためにさらに時間が必要な場合であるかなど、延長する合理的理由を検討しています(大阪読売新聞試用者解雇事件・大阪高判昭45.7.10・労判112-35、雅叙園観光事件・東京地判昭60.11.20・労判464-17)。
3 次に問題となるのが、試用期間との名称を用いない場合です。例えば、有期雇用契約を締結し、その期間に労働者の資質・能力を見極めて、期間満了契約終了後に優秀な者とだけ新たな無期契約を締結を契約するという契約形式をとった場合はどうなるでしょう。
有期雇用契約は期間満了により終了するため、通常は解雇権濫用法理は及ばず、上記1のような解約権行使の制限を受けないのではないかとも思えます。しかし、判例は有期雇用の趣旨・目的が能力や適性を評価するものであるときは、契約期間満了により当然に契約が終了する旨の明確な合意がある等の特段の事情がある場合を除いて、期間の設定は契約の存続期間ではなく試用期間であるとして、解約権行使の制限が及ぶとしています(神戸弘陵学園事件・最判平2.6.5・労判564-7)。
このように、契約形式よりも運用実態を実質的にみて、それに合わせたルールが適用されることになります。
4 試用期間を定める場合には、契約上の根拠を明確にする必要があります。したがって、試用期間の長さ、延長の条件、解約権行使の事由などについて、契約書や就業規則に明確に定めておくことが必要になります。期間の長さの設定については、合理的な範囲で認められるため、配属前研修に何をするかや配属後にどのような業務経験を積ませるか等について具体的な資料を残し、労働者の能力・資質を見極めるために設定した期間が必要であることを合理的に説明できるようにすることが必要です。
逆に、試用期間でなく有期雇用契約を締結したい場合には、本採用を期待せるような契約や運用にせず、期間満了により雇用契約が当然に終了することを合意し、実際の運用もそのように徹底します。
(就業規則による試用期間の定めの例)
| (試用期間) 第〇条 1 社員として新たに採用した者については、採用した日から〇か月を試用期間とする。 2 前項について、会社が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。 3 第1項について、会社の責めによらない事由により、試用期間満了までに社員としての適格性を判断できない場合、会社は、この判断のために相当な期間、試用期間を延長することがある。 4 試用期間中に社員として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第〇条(解雇)に定める手続きによって行う。 5 試用期間は、勤続年数に通算する。 |
- 経歴詐称していた社員への対応
- 採用内定取り消し
- 試用期間の性質と運用
- 試用期間中の者の本採用拒否
- 上司の指示に従わない社員への対応
- 残業しない社員への対応
- 欠勤を繰り返す社員への対応
- 取引先から金品を受け取っている社員への対応
- セクハラ行為をする社員への対応
- 厳しい叱責をする社員への対応
- ストーカー行為をする社員への対応
- 会社行事に参加しない社員への対応
- 備品を私的利用する社員への対応
- 会社のパソコンやスマートフォンを私的に利用する社員への対応
- 配転拒否する社員への対応
- 出向を拒む社員への対応
- 休憩時間中の電話当番の賃金を要求する社員への対応
- 無断残業で残業代稼ぎする社員への対応
- 繁忙期に長期休暇を取得する社員への対応
- 復職を一方的に要求する社員への対応
- 時間外手当を要求する年俸制社員への対応
- 正社員同等の賃金を要求するパートタイム社員への対応
- 不正請求を行った社員の損害賠償義務の精算
- 通勤手当を不正受給した社員への対応
- 問題社員の解雇
- 普通解雇と懲戒解雇の選択
- 懲戒解雇処分と退職金
- 勤務成績の悪い者への退職勧奨
- 退職後の機密保持の義務付け
- 他の社員の引き抜きをする元社員への対応
- 休日に職場の同僚に物品等を販売する社員への対応
- 勤務時間外に兼業している社員への対応
- インターネットに開発中の商品に関する書き込みをする社員への対応
- インターネット上で会社や同僚を誹謗中傷する社員への対応
- 社内不倫する社員への対応