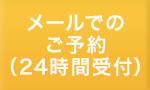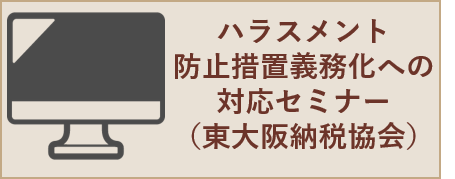復職を一方的に要求する社員への対応
Q X社では、交通事故に遭い首と腰を痛めたAと、発病によりこれまでの通常業務を行えなくなったBに対して休職を命じた。X社では休職期間を1年と定めて、傷病の治癒による復職ができないまま、休職期間が経過した場合には退職する旨が定められている。Aは休職満期直前に、復職可能という診断書を送ってきて、会社に対し一方的に復職を求めている。Bはこれまでの通常業務は行えないが、軽作業なら行えるとして、休職に応じず賃金の支払いを求めている。X社はどのような対応をすべきか。
A 1 まずは、従業員の疾病が業務に起因するものでないことを確認しましょう。以下では、業務外での疾病であることを前提に対応を検討します。
休職とは、ある従業員について労務に従事させることが不能又は不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し労働契約関係を維持させながら労務への従事を免除すること又は禁止することをいいます。従業員の傷病が一定期間続く場合に、使用者が継続年数や病気の性質などを考慮して、使用者が休職を決定します。
一般的には休職に関する規定が就業規則等で定められ、所定の休職期間中に従業員が治癒せず復職できなかった場合には自然退職や解雇が検討されます。就労不能により、従業員は労務の提供という労働者の基本的義務の履行ができないので、解雇の検討もやむをえません。
2 従業員が復職できるかは、疾病が「治癒」したかどうかの問題となります。「治癒」については、裁判例は「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復した」かどうかで判断しています(平仙レース事件・浦和地判昭40.12.16・労民16-6-1113)。そして、復職が可能であることの立証責任は従業員側にあります(国(在日米軍従業員・解雇)事件・東京地判平23.2.9・判タ1366-177)。
治癒の判断権者については、判例で「労働契約上、その内容の合理性ないし相当性が肯定できる限度において、健康回復を目的とする精密検査を受診すべき旨の健康管理従事者の指示に従うとともに、病院ないし担当医師の指定及び検診実施の時期に関する指示に従う義務を負担しているものというべきである」(電電公社帯広局事件・最判昭61.3.13・労判470-6)とされていることから、会社は合理性・相当性の認められる範囲で「治癒」判断のための医師を指定できると考えられます。
休職者は自己が選定した主治医の診断書を提出するのが通常ですが、会社としては会社が指定する専門医の診断書を提出するように可能な限り要請すべきです。なぜなら、主治医は求職者の求めるままに診断書を作成する場合や患者の治療を優先するあまり治療のためには患者の使用者である会社は無制限に協力しなくてはならないと考える場合があるからです。
また、会社として求めるべき「治癒」は従前と同様の労務債務を履行できるかということなので、治療にとって復職が望ましいかという休職者の主治医の観点は「治癒」判断にそぐわないからです。
一方的な復職を求める休職者への具体的な対応として、まず行うのは①復職判断のプロセスを明確に伝えることです。復職の前提となる「治癒」の判断は産業医の意見を踏まえて会社の人事部門が最終的な判断をすること、休職者の主治医の診断書も重要な判断資料として扱うことを伝えます。
②休職者に産業医の面談や診断を受けるように要請します。③休職者が産業医の面談を拒む場合には、産業医から主治医に対して診断の根拠となった資料の提示を求めることも考えられます。会社はこのような資料提示の求めをするか、主治医に対して職場で必要とする業務遂行能力に関する資料を提供して意見を求めるか等について産業医と相談し検討します。④実際に休職者が労務遂行能力を回復しているかの資料が足りない場合には、試し出勤(リハビリ出勤)をさせるなどして、資料を収集しましょう。
3 休職者が治癒に至っていない場合でも、復職させなければならない場合もあり、注意が必要です。
慢性的な傷病により、回復の見込みがなく、これまでの業務に従事することが出来なくなった社員であっても、①契約上職種の限定がされていない場合には、判例は「現に就業が命じられた特定の業務について労務提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。」(片山組事件・最判平10.4.9・労判736-15)としており、会社に復職可能性の十分な検討が求められています。
②職種限定の合意がある場合には、原則として従前の特定された業務に応じた仕事ができるまで回復していないならば「治癒」とは認められず、復職を認める必要はありません(参考裁判例:カントラ事件・大阪高判平成14.6.19・労判839-47)。ただし、職種限定があっても基本的な能力に低下がなく、短期間に復帰可能であれば、会社は他職種への復職可能性を十分に検討すべきであったとする裁判例(全日本空輸事件・大阪地判平11.10.18・労判772-9)もあるので、リスク回避のためには、職種限定があっても職種・配置転換の可能性を検討するプロセスを踏みましょう。
治癒には至っていないが、軽微な作業なら開始でき、ほどなく通常業務に復帰できる見込みがある場合については、会社は休職者と話し合い、一定の期間を明確に定めたうえで軽微な作業に就かせることを検討しましょう。裁判例でも、負担軽減や他部門への配置が可能であったのに、復職を認めなかった措置を無効としたものがあります(キャノンソフト情報システム事件・大阪地判平20.1.25・労判960-49、エール・フランス事件・東京地判昭59.1.27・労判423-23)。
4 従業員が復職できるかは、疾病が「治癒」したかどうかの問題となります。「治癒」については、裁判例は「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復した」かどうかで判断しています。会社としては会社が指定する専門医の診断書を提出するように可能な限り要請すべきです。Aについては、Aの選んだ医者の診断書ではなく、会社指定の医者の診断書を提出するように働きかけましょう。
A、Bについて「治癒」の判断を経たうえで、「治癒」に至っていないといえる場合には、職種限定の合意があるかを確認しましょう。職種限定の合意がない場合には、(労働者の)能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。」(片山組事件・同上)との判例があるため、会社に復職可能性の十分な検討が求められます。
職種限定の合意があれば、従前の業務ができない以上、基本的には会社に復帰させる義務はありません。ただし、職種限定があっても基本的な能力に低下がなく、短期間に復帰可能な場合には、会社は他職種への復職可能性を十分に検討すべきです。
- 経歴詐称していた社員への対応
- 採用内定取り消し
- 試用期間の性質と運用
- 試用期間中の者の本採用拒否
- 上司の指示に従わない社員への対応
- 残業しない社員への対応
- 欠勤を繰り返す社員への対応
- 取引先から金品を受け取っている社員への対応
- セクハラ行為をする社員への対応
- 厳しい叱責をする社員への対応
- ストーカー行為をする社員への対応
- 会社行事に参加しない社員への対応
- 備品を私的利用する社員への対応
- 会社のパソコンやスマートフォンを私的に利用する社員への対応
- 配転拒否する社員への対応
- 出向を拒む社員への対応
- 休憩時間中の電話当番の賃金を要求する社員への対応
- 無断残業で残業代稼ぎする社員への対応
- 繁忙期に長期休暇を取得する社員への対応
- 復職を一方的に要求する社員への対応
- 時間外手当を要求する年俸制社員への対応
- 正社員同等の賃金を要求するパートタイム社員への対応
- 不正請求を行った社員の損害賠償義務の精算
- 通勤手当を不正受給した社員への対応
- 問題社員の解雇
- 普通解雇と懲戒解雇の選択
- 懲戒解雇処分と退職金
- 勤務成績の悪い者への退職勧奨
- 退職後の機密保持の義務付け
- 他の社員の引き抜きをする元社員への対応
- 休日に職場の同僚に物品等を販売する社員への対応
- 勤務時間外に兼業している社員への対応
- インターネットに開発中の商品に関する書き込みをする社員への対応
- インターネット上で会社や同僚を誹謗中傷する社員への対応
- 社内不倫する社員への対応