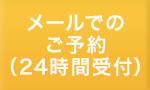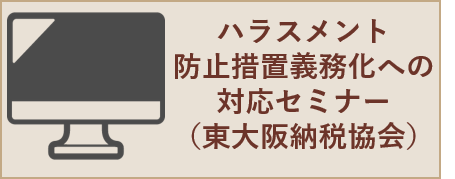第4 答弁書の書き方
1 概要
(1)労働者が労働審判を申し立てた場合には、使用者は相手方として、審判の第1回期日前に答弁書を作成・提出しなければなりません。答弁書は申立人が申立書に記載する「請求・主張・証拠」に対して、対応する事項を記載します。
一般に労働審判を含む民事紛争は「請求・主張・証拠」のピラミッド構造で成り立つと言われています。請求は当事者が裁判所に求める結論のことを言います(EX労働者による会社・使用者への残業代の請求)。
「主張」は請求を基礎づける事実の主張であり、「証拠」は主張の根拠となる人の証言(人証)、物(物証、書面含む)のことをいいます(EX会社による労働者が残業していなかった事実の「主張」、労働者の勤務時間を記録するタイムカードという「証拠」)。複数の証拠が主張を支え、さらに複数の主張が請求を基礎づけることになります。
民事裁判と労働審判に共通する注意点として、刑事裁判と異なり、真実の追及よりも紛争当事者の納得が重視されるということがあります。重要な事実について当事者双方が認めた場合には、それが客観的事実に反する場合でも裁判所はその事実があることを前提とした判断をします。したがって、答弁書では争う事実と争わない事実は明確に区別して記載する必要があります。
労働審判における特徴としては、民事裁判よりも簡易迅速な手続きを重視するため、申立書、答弁書の重要性が増しています。例えば、民事裁判では証拠となる陳述書は請求・主張を記載する書面とは別に提出しなければなりませんが、労働審判では答弁書に陳述書と同内容の記載していれば、陳述書を証拠として提出した場合と同様に扱われます。
(2)答弁書に記載すべき事項は労働審判規則16条1項に定められています。①申立の趣旨に対する答弁、②申立書に記載された事実に対する認否、③答弁を理由づける具体的な事実、④予想される争点及びその争点に関連する重要な事実、⑤予想される争点ごとの証拠、⑥当事者間でなされた交渉やあっせんその他申立に係る経緯、⑦代理人や相手方の住所・電話番号、ファックス番号などです。特に、答弁書提出の段階で、争点となることが予想される事項に関する証拠の記載、証拠書面の添付(規則16条2項)が求められていることに注意が必要です。
(3)答弁書等の準備書面の記載において特に重要となるのは、具体的な事実と証拠に基づく記載をすることです。具体的な事実を挙げ、それを証拠で裏付けることができるかどうかが紛争の勝敗を左右することとなります。労働者の解雇を争う事例で、いくら会社が労働者の能力不足を主張しても、それが抽象的な主張にとどまる限り、正当に評価されません。
能力不足というには、当該労働者に対して何年何月何日に顧客から苦情があったとか、他の社員と比較して営業成績がどれだけ低いか具体的に主張する必要があります。具体的な事実の主張においては、いつ・誰が・どこで・何故・何を・どのようにしたのか(5W1H)を意識して記載するようにしましょう。特に年月日と主語の記載が重要です。
実際に書面を作成するのは代理人弁護士である場合が多いので、打合せにおいて会社としては必ず客観的な資料・記録を持参して、具体的な事情を説明するようにしましょう。
労働審判は短期決戦でもあるので、一度審判委員会が抱いた心証を覆すのは難しいです。最初の書面の段階から、客観的な事実と証拠に基づき、的確な法的主張を行っていく必要があります。
2 証拠の提出について
労働紛争では、当事者で言った言わないの水掛け論による争いが生じることが多くあります。当事者主張の事実について客観的な記録がない場合には、労働委員会はどちらの主張も認めることはできませんし、そのような争い自体を取り上げないこともあります。そこで、文書、日報、日記、録音データなどの客観性の高い記録が重要となります。常日頃から、後日の紛争を想定しての労務の記録化が必要です。
通常の民亊裁判では証拠の提出は当事者の権能であり責任とする原則が妥当していますが、労働審判では簡易迅速な審理進行のため、審判委員会による職権での事実関係の調査、証拠調べをすることが認められています(職権主義、労働審判法17条1項)。
そのため、審判委員会が当事者(多くは会社側)に日報や報告書、営業成績などの客観的資料の提出を求めることがあります。これを断った場合には、断った当事者に不利に事実認定がされることがあるので注意が必要です。したがって、審判委員会の証拠提出の求めがあればこれに応じることが原則といえます。
以前の裁判実務では、隠し玉となる証拠を後にとっておき、相手方に虚偽の供述をさせた上で、それを崩す証拠を後出しするということが多く行われていました。しかし、現在は争点及び証拠の整理による迅速な紛争解決の観点から、このような手段は推奨されません。
特に労働審判では、有利な証拠を全て第1回期日前に提出しなければなりません。提出しなかった場合には、後に提出しようとしたときに提出できなかった合理的な理由の説明を求められることになり、証拠として認められなくなるリスクを負うことになります。基本的に出せる証拠は最初から全て提出するのが基本となります。
3 類型別申立・答弁方法
(1)解雇
解雇の有効性に関しては、個別法に解雇規制が置かれるうえ、一般に労働契約法16条により「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」との法規制が及びます。
実際の紛争においては、解雇事由ごとに「客観的に合理的な理由」及び「社会通念上の相当性」の有無を争うことになります。解雇事由に関しては、労働者の請求があれば使用者は遅滞なく書面で交付しなければならず(労働基準法22条1項)、使用者の特定する解雇事由が争いの対象となるので、解雇に際しては客観的な根拠に基づく理由の設定が必要です。
以下では、解雇事由ごとの留意点を述べていきます。
ア 非違行為、ミスを利用とする解雇
労働者の非違行為、ミスによる解雇は具体的には、職務懈怠、勤怠不良(無断欠勤、遅刻など)、業務命令違反、職場規律違反などに対して行われます。
この理由による解雇については、合理性や相当性が認められるかは具体的な事情に基づいて判断されます。もっとも、一般的に、些細な非違行為やミスを理由とする場合、事前に十分な注意や警告をしておくことが必要であるということがいえます。
注意や警告をしても改善が見られないなど、労働契約関係の継続が困難であるという事情が認められないと解雇権濫用として無効とされる可能性が高いです。答弁書では、当該労働者が非違行為をしたことの記録(始末書、報告書)、上司の指導及びそれに基づく改善の経過の記録を証拠として出すことが必要です。勤務態度の不良であれば、欠勤、遅刻がわかる日報、出勤簿、顧客からのクレームが記載されている記録、過去の懲戒処分歴などが証拠となります。証拠の提出の為にも、従業員の業務に関する管理・記録の体制を整備しておきましょう。
イ 個人の能力 適性欠如を理由とする解雇
会社の就業規則には解雇事由として、勤務成績・業務能力が著しく不良で業務に適さない場合が規定されていることが多いです。 このような類型の解雇に関しては、①労働者が能力不足であるか、②能力不足があるとしても一定の改善が見込まれないかどうかが問題となります。
①能力や適性の不良についてそれが解雇事由に当たると認められるかどうかは、具体的には事案ごとの判断となります。労働契約ごとに労働者に求められる能力・適性は異なるので、労働契約時に前提とされた能力・適性がどの程度のものかが特定されたうえで、客観的資料からその能力・適性が備わっていないことが証明できなければなりません。
一般的には、能力不足の程度が著しく、職務の円滑な遂行に支障が生じ、または生じうる蓋然性が高い場合に限定されています(セガ・エンタープライゼス事件・東京地決平11.10.15・労判770号、エース損保事件・東京地決平13.8.10・労判810号など)。答弁書では、能力不足については抽象的に仕事ができないと記載するのではなく、日報、営業成績の数値、顧客からのクレームの記録などから具体的な事実を記載する必要があります。
②能力や適性不足が認められた場合にも、一定の改善が見込まれる場合には、指導や教育訓練、配置転換などの解雇回避の措置を尽くさなければ、解雇権の濫用とされる可能性が高いです。答弁書では、注意・指導の面接記録等の提出とともに、具体的事実を主張することになります。
ウ 傷病による解雇
多くの企業では、労働者の私傷病による欠勤が長期間続いた場合には、これを休職として、休職期間満了時点でも復職が困難な場合には解雇や休職期間の満了により退職と扱う旨の就業規則の定めを置いています。このような事由による解雇の場合には、①従前の職に復帰することが本当に不可能か、②他の業務での労務提供が可能かが争われることになります。
①について、具体的な事実や証拠を基礎づけるものとして、医師による診断の結果(診断書)、意見書が挙げられます。判例では労働者は「労働契約上、その内容の合理性ないし相当性が肯定できる限度において、・・・病院ないし担当医師の指定及び検診実施の時期に関する指示に従う義務を負担している」(電電公社帯広局事件・最判昭61.3.13・労判470-6)とされていることから、会社は合理性・相当性の認められる範囲で私傷病治癒判断のための医師を指定できると考えられます。休職者は自己が選定した主治医の診断書を提出するのが通常ですが、会社としては会社が指定する専門医の診断書を提出するように可能な限り要請すべきです。
②については、片山組事件という重要な最高裁の判例があります(最判平10.4.9・労判736号)。この事案では私病を理由に休職していた労働者が、ある程度回復した段階で、従前の現場での業務ではなく簡易作業ならできるとして会社に復職を求めたところ、会社がこれに応じず休職命令を出して賃金を支払わなかったことから、有効な労務提供の有無、ひいては賃金請求権が争われました。
判断としては、労働契約が職種や業務内容の特定の無いものである場合には、労働者が現実に配置可能な業務について労務の履行ができ、かつ労務の提供を申し出ているならば、契約上有効な労務提供があるといえ、会社の賃金支払いの責任が生じるとしました(民法536条2項)。
この判例は、傷病等により従前の職務復帰が困難であることを理由とする解雇の場合にも妥当すると考えられています。したがって、従前の職務に復帰できなくとも、契約上及び労働者の治癒の程度から他に就労可能な職務がある場合には、配置転換を検討せずになされた解雇・退職扱いは無効となるでしょう(参考裁判例として、北産機工事件・札幌地判平11.9.21・労判789、東海旅客鉄道事件・大阪地判平11.10.4・労判771)、全日本空輸事件・大阪高判平13.3.14・労判793、北海道龍谷学園事件・札幌高判平11.7.9・労判764)。
答弁書においては、「配置の現実的可能性」がある職務がないことを主張し、その証拠を摘示することになります。「配置の現実的可能性」は労働者の能力・経験・地位、当該企業の規模・業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情に照らして判断されるので、労働者の評価や会社の業務上の限界などを示す客観的証拠を準備しましょう。
また、解雇は労働者の契約上の地位を失わせるものであるため、裁判所は労働者の地位に配慮する傾向にあります。会社が労働者の負担軽減や他の職種への転換等の解雇回避の措置を尽くしたかが問題とされる場合もあるので、解雇に至る面談等の記録も会社が労働者に配慮した証拠として残しておきましょう。
エ 復職を求めず金銭請求する場合
解雇された労働者は解雇の無効を主張し、①労働契約上の(労働者としての)地位の確認、及び②解雇期間中の賃金の支払いを求めるのが一般的です。もっとも、労働者の中には、復職して嫌がらせをされることへの懸念、解雇をめぐる会社の対応への嫌悪感から、復職を求めずに金銭的な補償を受けることのみを求めることもままあります。
しかし、日本の法律では現状、解雇時の地位確認に代えて金銭的請求をする権利を認めてはおらず、訴訟によりそのような請求をすることはできません。そこで、訴え以外による方法をとる必要があります。
一つ目が、とりあえず地位確認と賃金支払いを求めて提訴し、訴訟の中で行われる和解の中で問題解決を図ることです。
二つ目が、解雇を不法行為(民法709条)として損害賠償を請求する方法です。①精神的苦痛に対する慰謝料、②逸失利益、③退職金の差額、④弁護士費用を請求することが考えられますが、解雇が無効とされても不法行為とまでいえないと判断されること、不法行為と判断されても逸失利益や慰謝料がごく低額しか認められないことが多いです(セクハラの被害者が退職に追い込まれた場合は除きます)。
三つ目が労働審判での補償金の請求です。労働審判では、「当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判」をすることとされ(労働審判法1条)、「①当事者間の権利関係を確認し、②金銭の支払い、物の引渡しその他財産上の給付を命じ、③その他個別的労働関係民亊紛争を解決するために相当と認める事項を定めることができる」(労働審判法20条1項)とされています。
そのため、裁判よりも柔軟な紛争解決の方法を示すことができるとされています。そこで、労働者が「解雇は無効であるが、金銭による解決を図ってもよい」という意向を表明した場合は、審判委員会が「一定の金銭の支払いと引き換えに、労働契約関係が終了することを確認する」といった審判を下すことが可能であり、実際にも同様の審判が行われています。
この場合の具体的な主張としては、労働者側からの申立書での理由中の記載や審判期日における希望の表明を待つほかなく、会社側としては提案はできても、労働者側が望まなければ審判に反映されないと考えられます。
上記のように、地位確認に代えて金銭での解決を図る審判を出すことは、基本的に労働者側の意向によることになります。他方で、解雇を有効とする判断に至った場合に、金銭支払いを命じる審判を下すことは可能かも問題となります。一般的には訴訟で解雇が有効との判断がされれば、賃金も発生せず金銭支払いを認めることはできません。
しかし、審判では「事案の実情に即した解決」を柔軟に考えることができるところ、会社が退職金の上積みを条件に希望退職を応募していたが希望者が少なく整理解雇に至った場合、有効な配転命令を拒否した労働者が解雇されたが労働者に酌むべき事情がある場合、会社が金銭的解決を申出ている場合などには、解雇が有効とされても、金銭支払いを命じることで労働者が審判を受け入れやすくなり紛争解決が図られると考えられるので、そのような審判を下すことも可能であると考えられます。
(2)未払い残業代請求
未払いの残業代の請求に関しては、残業の有無が争点となります。労働者が弁護士を代理人として労働審判を申し立てた場合には、客観的証拠を揃えており、勝つ見込みをもっていることが想定されます。
この場合、労働者側はタイムカードや、日報、手帳の記載といったものを証拠として出してくると考えられるので、会社側は残業がないということの反証(申立人の請求を基礎づける立証を崩す主張・立証活動)をしなければなりません。
ここでも、会社側は客観的な根拠に基づく具体的な主張をしていかねばなりません。特にタイムカードが証拠として出された場合には、一般に客観的信用性が高いので、タイムカード記載の時間がそのまま労働時間であるという認定がなされてしまいます。
これに対しては、会社側はタイムカードの打刻時間と労働者が実際に業務を行った時間が異なることを立証しなければなりません。たとえば、労働者が業務に使用する電話、メール、パソコンの利用終了時とタイムカードの打刻の時間のずれが生じていることなどを、時間の記録データを証拠として主張することがあります。
会社がタイムカードなどの客観的方法で労働時間の記録をつけていない場合には、労働者が個人的につけている手帳・日記など必ずしも客観的な記録といえないものから労働時間が認定されることがあります。このような場合には、労働者が当該証拠を根拠に具体的に主張する事実と矛盾する客観的事実を示すことが効果的です。例えば残業したと主張する日に病欠していた事実などです。そうすれば、手帳や日記の記載の信用力を相当程度減殺することができるでしょう。
また、残業時間についてはあくまでも業務命令に基づかなければ労働時間とは認められないのが原則です。もっとも、会社や直属の上司が労働者の残業の事実を把握していながら、黙認している場合には黙示的な命令があったと認定されることがあります。労働者の無断での残業を否定するには、会社が積極的に残業禁止の命令を行っていた等の事実の主張・立証が必要となります。
残業代含む未払いの割増金については、さらに付加金の請求が問題となる場合があります。労働者が請求したときには裁判所は未払い額と同額の付加金の支払いを命じることができるとされています(労働基準法114条)。条文上、付加金を命じる主体が「裁判所」とされるため、労働審判を下す労働審判委員会が付加金の支払いを命令する審判を出せるか問題となり、裁判所によっても扱いが異なるようです。
そして、審判として付加金支払いの命令はできないと考える裁判所であっても、付加金の請求が2年の除斥期間にかかること(労働基準法114条但書)、労働審判が訴訟に移行する場合があること(労働審判法22条1項)を踏まえて、労働者が申立において付加金の請求を行うことは認めています。
(3)人事異動の無効を前提とする請求
ア 人事異動には、大きく分けて①配転(同一企業内での職務内容、勤務地の変更)、②出向(企業との労働契約関係を維持しながら、他企業で相当長期にわたり当該他企業の労務に従事させる人事異動)、③転籍(企業との現在の労働契約関係を終了させ、同時に他企業との新たな労働契約関係を成立させて他企業の労務に従事させる人事異動)があります。
このような人事異動は、労働者の労働条件の大きな変更となるので、不満を持った労働者が従前の地位の確認を求めて、人事異動に係る命令の無効を争うことがあります。
争点となるのは、そもそも使用者に人事異動の命令をする労働契約上の権限があるか、そして使用者に権限が認められるとしても権限の濫用とならないかです。①配転、②出向、③転籍の各類型ごとに、答弁書作成にあたっての留意点を説明していきます。
イ ①配転
配転命令権の根拠としては、個別的な労働契約、就業規則や労働協約に使用者の配転命令権が規定されていることが必要とされます。具体的な規定については、能力開発の必要性・雇用の柔軟性確保の要請から、「業務上の都合により配転を命じることができる」旨の概括的記載で構わないと考えられています。そして、配転命令権の範囲については、職種、勤務内容、勤務地を限定する明示または黙示の合意がある場合には、その合意の範囲となます。
会社としては、配転命令の有効性を示す証拠として、配転命令権についての規定を置く文書、合意形成に関する契約書や契約締結過程の記録を準備する必要があるでしょう。限定の合意については、主に労働者の申立における主張・証拠に対応していくことになります。特に職種の限定が争われるのは、医師、看護師、放送局のアナウンサーなど特殊な技能・資格を前提に採用されている場合です。
配転が使用者の配転命令権の範囲内であっても、権限濫用であれば配転命令は無効となります(労働契約法3条5項)。濫用か否かは、一般に配転の業務上の必要性の程度と配転によって労働者が被る不利益の程度とを比較衡量して判断されます。
具体的には、東亜ペイント事件(最判昭61.7.4・労判477)の挙げる規範がメルクマークとなり、配転の業務上の必要性がない場合、または必要性があるとしても、他の不当な動機・目的による場合若しくは労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与える場合には濫用と判断されます。
まずは、使用者としては配転命令の業務上の必要性を客観的資料に基づき主張することが必要です。業務上の必要性については、業務運営上の合理性が認められる限り、広く必要性が認められると考えられます。他の不当な動機・目的は、典型例として退職への追い込みや労働組合つぶしのために閑職、過酷な業務への配転があげられます。
不当な動機・目的については使用者は労働者側からの主張を受けて、必要があれば業務上の必要性による配転であることをより基礎づける資料をさらに提出する等の対応をとります。通常甘受すべき程度の不利益か否かについては、裁判例の傾向として、単身赴任による家族別居の程度は通常のものとされていますが、病気の者の看護、高齢者の介護の必要がある場合には配転で看護・介護に支障が生じる場合は不利益が著しいとして配転無効の判断をしています(育児介護休業法26条参照)。
ウ ②出向
出向命令権の有効性判断の構造は基本的に配転の場合と同様です(労働契約法14条)。
ただし、出向の場合は労務提供の相手方が代わり(民法625条1項)、労働条件の変更を伴うため、単に就業規則等に「出向を命じることができる」という概括的な規定があるだけでは足りず、就業規則、労働協約、個別の労働契約、採用時における説明と同意等により、①出向命じ得ること自体が明確になっていること、②出向先での基本的労働条件等が明瞭になっていること等が必要と考えられています(新日鐵事件・最判平15.4.18・労判847)。
権利濫用か否かについては、出向の業務上の必要性や、人選の合理性と労働者の被る不利益などの事情を考慮することになります(労働契約法14条)。
エ ③転籍
転籍は現在の労働契約を終了させて、労働者に他社との新たな契約関係を結ばせるものなので、配転や出向のように、就業規則等に転籍条項があれば使用者に命令権限が認められる
というものではなく、労働者の個別的同意が必要となります(労働契約法6条参照)。
この場合には、争いの中心は労働者の同意の有効性となります。会社としては、労働者が主張する意思表示の瑕疵(真意でない同意、虚偽表示、心裡留保、錯誤、詐欺・脅迫)や同意内容の公序良俗違反(民法90条)などの主張に対して反論することとなります。
(4)労働条件の不利益変更の無効を前提とする請求
ア 労働者の賃金、労働時間、休日等の労働条件は、労働者と使用者との合意によって決めるのが原則です(労働契約法3条1項、8条)。したがって、使用者が労働者の同意なく一方的に労働者の労働条件を引き下げることは許されません(労働契約法9条本文)。
ただし、法は労働者保護や労働条件の統一の要請から、労働条件の合意原則に一定の制限を設けています。社会一般の労働条件の最低基準を定める労働基準法の定める基準に達しない労働条件の合意は無効で、無効となった部分は労働基準法の基準が適用されます(労働基準法13条)。
また、就業規則の条件に達しない労働条件についての同意も無効で、無効部分は就業規則の基準が適用されます(労働契約法12条、労働基準法93条)。ただし、就業規則より労働者に有利な労働条件の合意(特約)は就業規則で無効とはなりません(労働契約法7条但書)。
さらに、労働者に労働協約の効力が及ぶ場合、労働協約に反する労働条件の合意は無効となり、労働協約の定める基準によることになります(労働組合法16条)。就業規則と労働協約では労働協約が優先します(労働契約法13条)。
イ 以上の合意原則に対して、実際には企業の経営上の必要性から、労働条件の切り下げが行われています。その態様としては、同意による切り下げ、就業規則の作成・変更による切り下げ、労働協約による切り下げ、人事権行使による切り下げなどがあるので、各態様ごとの留意点をあげていきます。
ウ 同意による切り下げ
労働者の個別的同意のある労働条件切り下げは原則として有効です。ただし、労働基準法や就業規則、労働協約の定めを下回る内容の切り下げは上記のように効力が認められません。また、同意内容が個人の尊厳や男女平等などの法の基本原則に反する場合もその同意は無効となります。
争点となるのは同意の有効性であり、意思表示の瑕疵(錯誤、詐欺、強迫など)が主張されることになります。
特に賃金の引き下げについては、労働者に及ぼす影響が大きいことから、労働者の自由な意思に基づいて行われたと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在しなけければ真意による同意と認められず、同意があったとはいえないと考えられています(アーク証券(本訴)事件・東京地判平12.1.31・労判785)。この場合には会社としては、労働者が切り下げに合意する旨意思表示したとか、記名押印のある同意書面があるという事実にとどまらず、合意の過程において強制の契機がなかったという実質的な主張をすべきと考えられます。
エ 就業規則の作成・変更による切り下げ
まずは、就業規則の作成・変更においては手続上の規制が及びます。使用者は、過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見聴取義務(労働基準法90条)、就業規則の労働基準監督署への届出義務(同法89条)、労働者への就業規則の周知義務(同法106条1項)を負うこととなり、これらの手続きを欠く就業規則の作成・変更は効力を有しません。
就業規則の作成・変更による労働条件の不利益変更は原則として禁止されていますが(同法9条本文)、上記の手続的要件を満たし労働条件の不利益変更の合理性が認められる場合には不利益変更が例外的に認められている。
不利益変更の「合理性」の判断においては、①就業規則の変更による労働者が被る不利益の程度、②使用者側の変更の必要性の内容・程度、③変更後の就業規則の内容自体の相当性、④代償措置、激変緩和措置、その他関連する他の労働条件の改善状況、⑤労働組合等との交渉経緯、⑥他の労働組合又は他の従業員の対応、⑦同種事項における社会における一般状況等を考慮して判断することになります。
この合理性の判断は検討する事項が多岐にわたり、複雑な判断を要するので、労働審判になじまない事案として手続きが打ち切られることも考えられます(労働審判法24条1項)。したがって、働審判で争われる場合は、手続的要件が問題とされる場合であると考えられるので、会社としては手続的要件の充足を基礎づける客観的資料を準備する必要があります。
オ 労働協約による切り下げ
労働協約には使用者と労働組合の交渉を経て締結される協約であり、当該労働組合所属の組合員の労働契約を規律するのみならず(労働組合法16条)、一定の条件を満たせば組合に加入していない労働者の労働契約についても規律する効力を持ちます(労働組合法17条)。このような効力は規範的効力とよばれます。
労働協約の締結においては、①書面に作成し、②両当事者が署名又は記名押印することで効力が認められます(労働組合法14条)。①②の要件を満たせば、基本的には労働条件の引き下げにも規範的効力が生じることになります。この点に関しては、会社は労働協約の書面を証拠として準備すれば、答弁は容易でしょう。
労働協約による労働条件の不利益変更の効力が争われる場合に問題となるのは、労働組合の協約締結権限です。第1に、すでに発生した個人の権利を処分や組合員を退職させる取り決めなど個人の権利性が強いものについては、組合員個人が特に組合に授権していない以上組合が勝手に処分することはできないと考えられています。
第2に、特定層の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的とするなど、労働組合の本来の目的である「組合員の労働条件・待遇の維持改善」に反する協約を締結することも権限外です。
第3に、組合内での民主的手続きを欠く場合にも、組合側の協約締結者の代表権限が否定されることになります。これらの点については、労働者の申し立てに対して、事実確認の上、反論をしていくことになります。
(5)労働者の人格権侵害(セクハラ・パワハラ)に係る請求
ア 人格権侵害に対する請求
労働者が人格権や性的自由などを侵害するセクハラ・パワハラ等の行為を受けた場合、その加害者や使用者に対しては、①損害賠償の請求(民法709条)、②問題となる行為をやめる、またはやめさせる請求(差止請求)、③就業環境整備のための具体的措置を求める請求をすることが考えられます。
イ 各請求の根拠、相手方
(ア)①損害賠償請求
法律上保護された利益である人格権や性的自由を侵害する行為(不法行為)がある場合、その行為により被った損害の賠償を請求することができます。セクハラ・パワハラの事例で考えられる損害としては、精神的苦痛に対する慰謝料、セクハラ・パワハラで退職に追い込まれた場合の賃金や自己都合退職と会社都合退職の退職金の差額といった逸失利益、弁護士費用などです。
このような損害賠償請求は、第一次的にはセクハラ、パワハラの加害者に対してなされます。もっとも、労働審判においては「個々の労働者と事業主」との間の紛争の解決を目的とするので(労働審判法1条)、加害者が上司・同僚のような労働者である場合には、加害労働者のみを相手方として申立をしても不適法として申立が却下されてしまいます。そこで、加害労働者のパワハラ・セクハラに関する使用者の責任を追及する法的構成が必要となります。
そのための法的構成としては、民法715条に基づく使用者責任、労働契約法5条や雇用機会均等法11条に基づく使用者の職場環境整備義務違反の責任(民法415条または同法709条)を問うことが考えられます。
なお、労働審判に加害労働者を参加させるには、労働審判の申立と同時に、利害関係人の手続き参加の申立を行うことになります。
(イ)②差止請求
人格権の侵害については、損害賠償の請求による事後的な回復だけでなく、侵害行為自体をやめるように請求することが一般に認められています。
労働審判では事業主を相手方として申立をする必要があるので、①の場合と同様に使用者に民法715条に基づく責任や職場環境整備義務違反の責任を問い、加害労働者にパワハラ・セクハラ行為をやめさせせることを請求することになります。
(ウ)③就業環境整備のための具体的措置を求める請求
この請求は、労働契約法5条や雇用機会均等法11条の使用者の職場環境整備義務を根拠にするものですが、このような使用者の義務については、労働者から義務違反の責任は問えても(上記②の請求)、使用者に具体的行動を求めることができる労働者の権利まで認めるものではないとして、訴訟での請求は困難です。
他方で、労働審判においては「当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判」をすることとされ(労働審判法1条)、法律上の権利や地位の確認や給付の請求に加え「その他個別的労働関係民亊紛争を解決するために相当と認める事項を定めることができる」(労働審判法20条1項)とされています。そのため、労働審判では通常訴訟の判決では下せないような審判を下すことが可能です。
そこで、労働審判では、労働契約法5条や雇用機会均等法11条の職場環境整備義務を根拠に、使用者に対してセクハラ・パワハラについて労働者啓発のための措置を講ずべきことを請求することが考えられます。
ウ 立証上の留意点
セクハラ・パワハラの事案で主に争われることになるのは、①セクハラ・パワハラ行為の存在、②使用者責任の有無です。
①については、セクハラ・パワハラが密室的状況で行われる場合が想定されるため、申立人が行為の存在を客観的に基礎づける十分な証拠を準備する必要があります。例えば、録音テープや電子メールの写しなどが客観的証拠となります。また、セクハラについては合意の上であったかどうかも問題となります。もっとも、加害労働者はともかく、事業主・会社としては、行為の存在自体を争うのは労働者側の主張・証拠に虚偽や合理的疑いがある場合でよいでしょう。
②については、事業主・会社は、行為が会社の全く知らないところで行われ、職務と関係のない私的行為として行われたとして、使用者責任を回避する主張することがあります。この場合には、加害者の職務上の地位、被害者と加害者の職務上の関係から、それが職務に関連した強制によるものかが争われることになります。
エ 労働審判利用の是非
労働審判は原則3回以内の期日で審理を終結させるため、事実関係が複雑である場合、考慮事項が多岐にわたる場合などには、労働審判になじまないとして手続が打ち切られてしまいます(労働審判法24条1項)。
セクハラ・パワハラの事案では、密室的なセクハラの認定や同意の認定など事実関係が複雑な場合や客観的証拠がない場合があり、労働審判では被害の実態解明が難しいことがあります。その点は、労働審判を利用するデメリットといえます。
他方で、労働審判は原則非公開の手続きであるため、セクハラ事案で被害者のプライバシー保護が図られること、企業側としてもセクハラ・パワハラが広く知れ渡ることが防げることから、その点で利用するメリットがあるといえます。
セクハラ・パワハラ事案の場合には、事案の特徴から、労働審判の利用の是非を慎重に検討する必要があります。
(6)仕事上のミスを理由とする損害賠償
ア 労働者が仕事上のミスで会社に損害を与えた場合には、会社が労働者に損害の賠償をすることがあります。労働者の行為で会社に直接損害生じる場合や、労働者が職務上の行為により第三者に与えた損害を会社が賠償し(民法715条)、それについて会社が労働者に求償する場合などが考えられます。
問題となるのは、労働者に賠償義務があるか、義務がある場合にどこまでの範囲で負うかという点です。
イ 賠償義務が問題となる場合
(ア)仕事上のミスといえない場合
損害賠償責任を問うには、故意・過失が必要となります。
労働者が職務の過程で通常求められる注意義務を尽くしている場合には、「過失」がないので損害賠償義務が生じません。例えば、取引先が倒産したために内掛金や貸付金が回収不能となった場合の担当者、自動車運転中のもらい事故の場合の運転手などです。
(イ)些細な不注意による場合
損害の発生が日常的に一定生じうる性質のものである場合には、労働者の不注意によるものであっても損害賠償義務は発生しないと考えられます。例えば、飲食店で食器を割る、つり銭を渡し間違うなどの軽微なものです。
ウ 労働者の負担の範囲
労働者が賠償義務を負う場合でも、損害の全額について賠償義務は負わないのが原則です。判例は「諸般の事情を考慮し、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ」賠償義務を負うものとします(茨城石炭商事事件・最判昭51.7.8・判時827号)。
具体的な賠償額については、ケースバイケースで、その判断基準となる事情として、使用者の事業の性格・規模・施設の状況、労働者の業務内容・労働条件、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度、労働者の置かれた状況・資力が挙げられます。
例外的に、労働者がミスとさえ言えないような窃盗や横領の犯罪行為により、使用者に損害を生じさせた場合には全額の損害賠償が認められるでしょう。
エ 労働者に対する損害賠償で留意する点
労働者に損害賠償義務が認められる場合に、使用者としては給与から賠償額を天引きできできれば簡便ですが、これは可能でしょうか。
この点については、会社は労働者に賃金を全額支払う義務を負うため(労働基準法24条)、会社が一方的に天引きを行うことは認められません。
ただし、労働者が自由な意思に基づいて、使用者に対して自己の負う損害賠償債務と賃金債権を相殺することに同意した場合は、天引きによる相殺が認められます。同意が自由な意思によるものと認められるには、自由な意思と認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要とされています(日新製鋼事件・最判平2.11.26・労判584号)。会社としては、労働者に半ば強制的に同意を求めて、労働者がやむなく同意したという場合には、自由な意思によるものと認められないので注意を要します。
また、会社が損害賠償を請求しない代わりに自主退職させること、給与からの天引きで賠償額を払い終えるまで退職させないことを強制的に行うことは認められません。
(7)労災による損害賠償
ア 労災保険と損害賠償
業務上の事由に基づく労働者の負傷、疾病、障害、死亡については、労災保険による補償(労災給付)が受けられます。労災保険では5人未満を使用する農林水産業を除いて、使用者が加入手続きをしなくても、当然に労災保険関係が成立することになります。
労働災害については、使用者は安全配慮義務違反(労働契約法5条)による債務不履行の損害賠償責任、故意・過失に基づく不法行為や製造物責任による損害賠償責任を負います。
損害賠償では、①治療費などの積極損害、②休業損害、逸失利益などの消極損害、③慰謝料などが請求でき、労災保険では①は全額補填、②は一部の補填となり、③は全く補填されません。そのため、労災保険による補填を受けている場合でも補填のない部分については損害賠償請求の検討の必要があります。
イ 損害額の算定
(ア)すでに労災保険による給付を受けている場合、労災保険による給付は損害の補填とみなされるため、その給付額は損害額から控除されます。
ただし、控除されるのは口頭弁論終結時までに支給が確定しているものに限られます(最判平5.3.24・判時1499号)。例えば、死亡の事案で労災保険で遺族補償給付(年金)がなされている場合に控除の対象となるのはすでに受給済みもしくは支給決定がされているものに限られ、口頭弁論終結時以降に受給する予定の遺族年金が損害額から控除されることはありません。
また、控除できるのは同一の損害項目に限られるので注意が必要です。
(イ)労災に対する補償であっても、福祉事業として行われる特別支給金等については、損害填補の性質を有しないため、損害賠償請求額から控除する必要はありません(コック食品事件・最判平8.2.23・労判695号)。
休業補償については、労災保険本体から平均賃金の6割が支払われ、労災福祉事業として平均賃金の2割の特別支給金が支給されるところ、前者の6割は控除対象となり、後者の2割は控除対象とならないので、結論として損害賠償においては休業損害として給与の4割分を請求できることとなります。
(ウ)労働者に過失がある場合
損害額からの労災給付額の控除は、消極損害、積極損害、慰謝料などの同一費目内でのみ許されることから(青木鉛鉄事件・最高裁昭62.7.10・判時1263号)、過失相殺の場合にに注意すべきことがあります。
労働者に80%の過失がある場合、損害賠償請求で認定される治療費や休業損害額は、実際に生じた損害の20%となります。すでに労災保険給付の療養補償給付で治療費の全額、休業補償給付で平均賃金の60%の給付を受けていれば、治療費(積極損害)、休業損害(消極損害)についてすでに賠償請求できる20%を超える給付を得ていることになります。
この過払いとも思える部分については、損害賠償請求における治療費・休業損害の20%の請求は控除により棄却されるのは当然として、20%を超える給付分がさらにマイナスに計算されることはありません。損害賠償請求で慰謝料の請求をしている場合には、休業損害、治療費とは損害費目が違う以上、休業損害、治療費の過払い分を慰謝料額から控除することはできません。
損害の費目を考慮せず、単純に損害総額から労災の給付額を控除することは誤りであるので、損害額の争いをする場合には注意する必要があります。
ウ 労災に係る損害賠償請求での労働審判の利用
労災での損害賠償請求のためには、労働者は使用者の安全配慮義務違反を立証せねばなりません。労働審判では原則3回以内の期日で審理を終結させるため、事実関係が複雑である場合、考慮事項が多岐にわたる場合などには労働審判になじまないとして手続が打ち切られてしまいます(労働審判法24条1項)。
例えば、過労死のような非災害性の労災の場合には、使用者の安全配慮義務違反の有無が争われ、複雑な審理が必要となります。使用者が安全配慮義務違反を認め、賠償額だけの争いがある場合を除いて、労災での損害賠償請求については労働審判になじまないといえます。
使用者の安全配慮義務違反が明らかな場合については、労働審判の活用が考えられます。